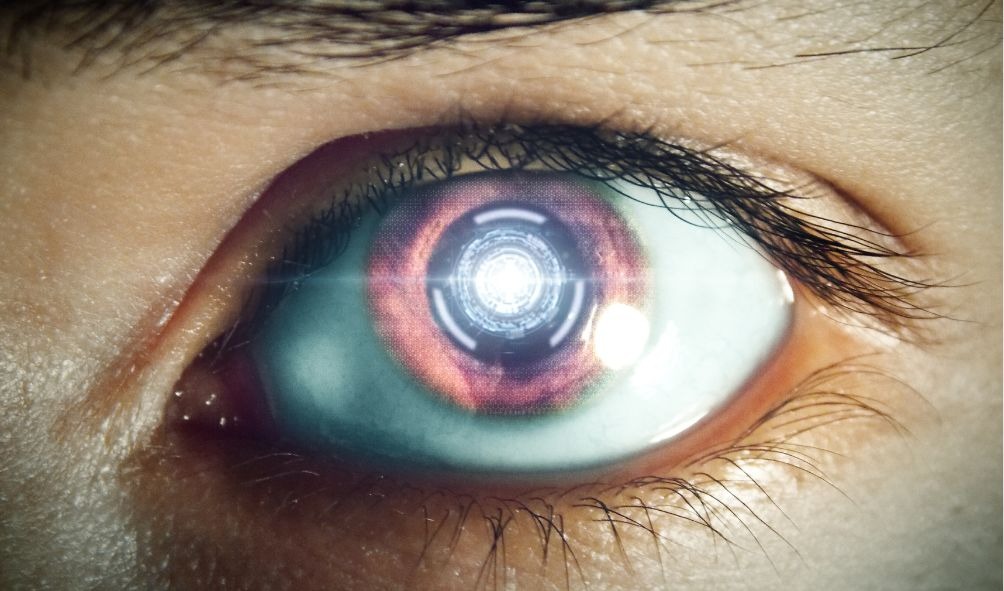“未来が見える”というと、なんだか小説や映画の話のようでリアリティがなく感じられるかもしれませんが、力のあるカウンセラーになると、未来が見えるようになります。
人は皆、毎日あらゆる選択をしながら生きていますが、その選択の基準や拠り所となるのが、自我状態や人生脚本、禁止令など様々な要素で構成された、その人の人格や性格と呼ばれるものになります。
何も考えずに適当に選択していると思えることも、実は無意識に自分なりの基準を持ってきちんと選択しているのです。
だから、傾向やタイプなどが自然と表れてきますし、それは好みの人物や物事を自発的に選ぶ時だけでなく、悩みや問題など、自分では求めていないけれど自然に起きていると思われるものや、向こうからやって来るものも同様に、その人の傾向に合ったものを受け入れているというのが理解できるようになります。
「いつも同じようなことで悩まされる」
「こんな問題ばっかり、もう嫌」
と思われたことがある方も多いかもしれませんね。
なので、心理学を学ぶ中で人物像を分析していくと、その方の抱える問題や選択の傾向が読めるようになり、その方がどのような人生を送られるのかまでを具体的に思い描く訓練をしていくため、それを繰り返していくうちに精度が上がり、自分でも気づかないうちに比較的高い確率で未来が見えるようになっていきます。
そして常に、より良い未来のためにどうしていくのが最善か、という視点で物事を見るようになるので、私生活においても、問題の種を見つけた段階で対処できるようになります。
それは実に、なんだか強くなれたような感覚とでも言いましょうか、なかなかに良い気分ですwww
ただ、普通は、問題が起きてから初めて気付き、慌ててそれに取り組むというのが一般的なので、カウンセラーの感覚は『普通とは違う』ということを理解しておかなければなりません。
自分は先読みできているから、相手の言動の将来への危険性を必死に説明するけれども、相手にはそれを受け取る準備ができておらずサッパリ理解できないので、齟齬が生じるという場合もあります。
このような現象が、カウンセリングの中級程度の習熟度の段階で起きてきます。
私も実際に、クライエントさんにどんなにロジックを説明してもただのお仕着せになってしまう、という時期がありました。
私生活でも、夫の子供への接し方を何度も注意・懇願し、問題がほんのちょっとでも顕在化してきた時にはすかさず指摘するも全然理解してもらえず、徐々に疲弊し信頼関係の構築を一方的に諦めてしまい明るい未来を思い描けない、という時期がありました。
同じ場所にいるけれど違うレイヤーにいるという時空の違う世界という漫画のような世界を、いつの間にか実体験していたのですね。
ただ、それらの体験を後悔や黒歴史だとは思っていません。
そういった“もがき”を経なければ、見えない世界もあります。
失敗からの学びを積み重ねることで、職業人として、人として、成長し深みが増していくという経験を重ねることが、またカウンセラーとしての成長に繋がっていくのです。
初めての経験も失敗も、人生で起きること全てが『肥やしになる』、そう考えると、カウンセラーって本当にお得な職業だなぁと思いますよね。
カウンセラーは、クライエントさんのご相談をお伺いする際に、カウンセリング開始から10~15分のインテークの時点で、クライエントさんの人物像の分析を基に見立てを立て、最終的な着地点に向けたアプローチまでを組み立てなければなりません。
カウンセラーの皆さんは、それができていますか?
カウンセリング業務に従事しながらも、クライエントさんはおろか、自分自身の未来さえ具体的に思い描けていないという方は、カウンセラーとして危機感を持たれた方が良いかもしれません。
クライエントさんの人物像や未来がリアルに思い描けるようになれば、自信を持って堂々とカウンセリンができるようになります。
そうなりたい、と思われる方は、ぜひご相談ください。
1人ひとりに合わせた短期集中型のセミナーで、的確なポイントやコツを無駄なく習得、カウンセリングスキルの激的な向上をお手伝いします。