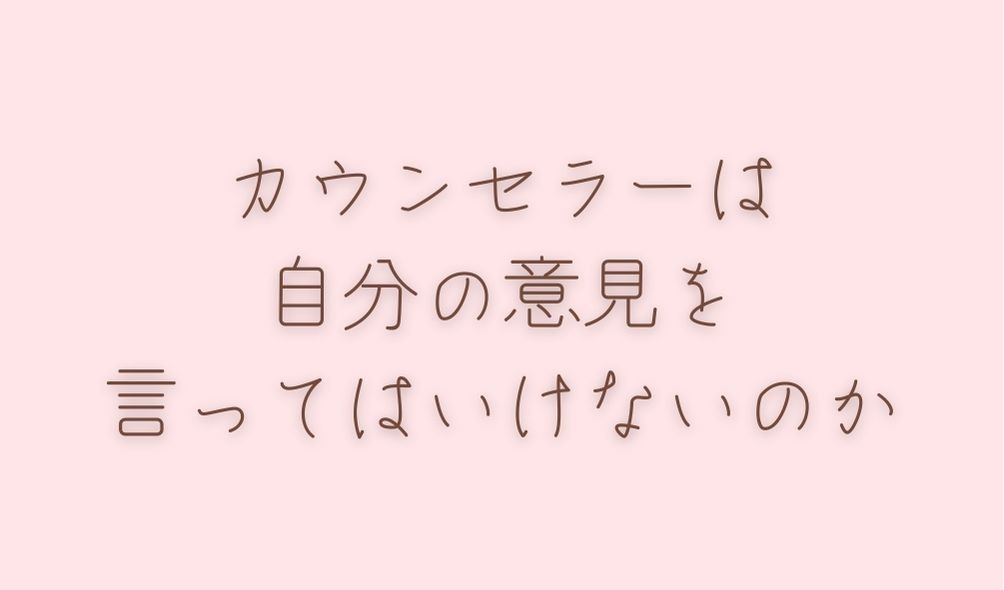多くのカウンセリング講座で、カウンセラーは自分の意見を言ってはいけない、と習う場合があります。しかし、我々カウンセラーはロボットではありませんから、感情や思考、それぞれに異なる価値観を持って生きる人間です。クライエントさんも、カウンセリングに来てロボットに向かって淡々と悩みを呟くわけではありません。“人と人”との信頼関係のもと、悩みの解決に向けて人間的成長を図っていくのがカウンセリングですから、カウンセラーは1人の人間として向き合わなければなりません。
人のコミュニケーション方法として、言語によるものは10%程度にしか過ぎず、視線や表情、姿勢、身振りなど、非言語により表現されるものが大半を占めるというメラビアンの法則をご存知でしょうか。つまり、口を閉じていても、感情や思考は無意識に身体全体から表現されており、言葉として発していなくても相手には伝わるようになっています。
意見を言ってはいけないとしても、相手に対して心の中で否定的な感情や懐疑心を抱いていると、黙っていても駄々洩れなのです。もっと悪いのは、目の前のクライエントさんを肯定しているように見せかけておいて心の中では嫌っているということは、堂々と嘘をつき続けているということです。これでは信頼関係なんて築けませんから、カウンセラーの意見を言ってはいけない、という教えは納得ができませんよね。
カウンセラーは、自分の感情や意見は素直に伝えるべきだと、私は思っています。
相手の気持ちに共感できるか出来ないか、考え方や価値観に対して率直にどう思うのか。
同じ場所に立ち視線を合わせ、クライエントさんのより良い未来に向けて真剣に考えているカウンセラーの姿勢が伝わることで、1人の人間として尊重されていると感じられるようになるからです。「1人じゃないんだ」という安心感が、新しい一歩を踏み出す勇気を支えてくれるのです。
それでは、「どうしても良く思えない」「はっきり言って嫌い」など相手に対して嫌悪感を抱いてしまった場合はどうしたらよいのでしょうか。
答えは簡単です。自分では対処できかねる旨を伝え、他のカウンセラーに相談していただくよう辞退します。そうすれば嘘をつく必要もなくなり、何よりもクライエントさんのお金と時間と労力を無駄にせずに済みます。せっかく相談してきてくれたのに申し訳ないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、どのような状況においても、カウンセラーとして提供できるクライエントさんにとっての最大の利益とは何かを考えると、判断しやすくなるかと思います。
ただし、これらを実現するためにはカウンセラーが自分自身をよく理解し、揺るぎない価値観を持っておく必要があります。どのような問いかけに対しても真直ぐに応えられるバランスの取れた思考、相手を尊重する素直さ、異なる価値観を受け入れられる柔軟性など、率直な意見の裏打ちとなる人間力がカウンセリングの度に試されているわけですから。どんなにキャリアを積もうと慢心することなく研鑽を積み続けられる謙虚さを忘れてはならないと思いますよね。