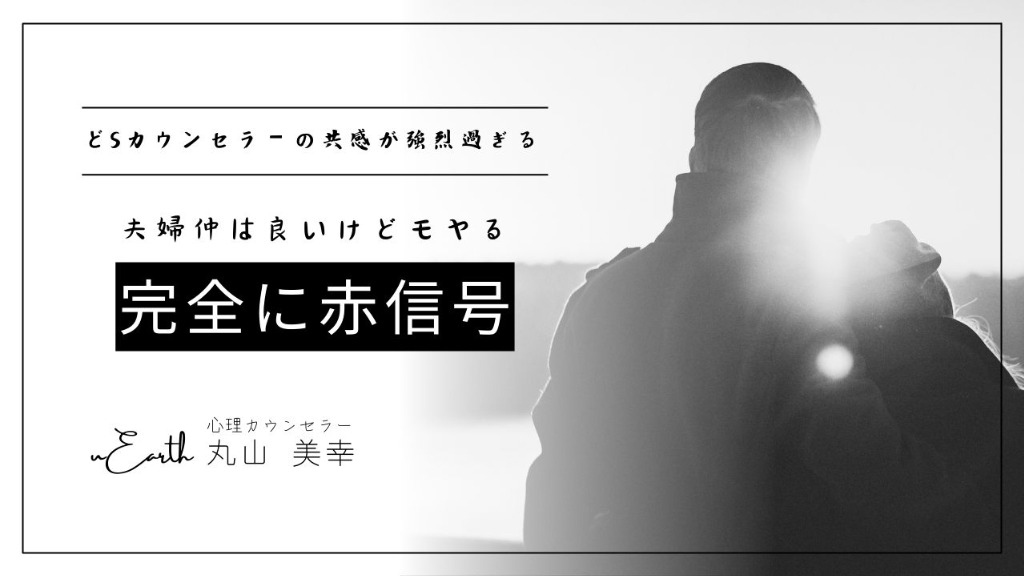私がお受けしているカウンセリングの専門ジャンルは、人間関係全般です。老若男女を問わず、日々様々な方からご相談をお受けしています。明確に悩みとして自覚している方もいらっしゃれば、悩んではいないけれど話を聴いて欲しいという方、よく分からないけれど違和感があるなど、苦しみの段階は人それぞれです。
悩みとは、人が成長するための試練として、その人が乗り越えられるよう最適な形で現れますので、その人の感度により悩みに気付くタイミングも異なります。自分ではそこまで深刻ではないと思っていても、わざわざカウンセラーに相談に来るという行動を時間と労力とお金を使って取っているわけですから、そこには大切な意味があるはずです。
カウンセラーというのは、話を聴くという受け身の仕事ではありません。クライエントさん自身も自覚できていないその大切な意味を、こちらから掴みに行くというアグレッシブな作業なのです。傾聴=アクティブ・リスニング、とはまさにこのことです。
本日ご紹介するエピソードでは、なぜ今このタイミングで相談に来られたのか、その意味を掴みに行きます。
【相談内容】
30代 女性 Bさん
4児(9~1歳)の母で専業主婦。
経済的に余裕もあり、生活は恵まれている。
特に困っていることはないが、少しだけモヤモヤする。
夫婦仲も良いのに、わがままなのだろうか?
■主訴
恵まれているのにモヤモヤするのはわがまま?
■人物像
CP、FCが高く、明るく快活な頑張り屋さん。
自意識が高い。
禁止令/自然に感じてはいけない
ドライバー/人を喜ばせろ、強くあれ、努力しろ
■見立て
専業主婦として4人の子供達の安全を守らなければという緊迫感の張りつめた日々。
絵にかいたような幸せな家庭生活でも、誰にも理解してもらえない孤独感を抱えているのでは。
いつも素敵なママでいなければ、という高い理想の中で苦悶。
夫からの不動の愛に確証が持てず、精神的な支えとなるものがない不安感。
この分析をもとに、共感して主訴に応えた一言がこちらです。
「完全に赤信号」
このケースは、現時点で特別な問題が起きているわけではないため、緊急性は無いように思われるかもしれません。頑張り屋さんのBさんは、大黒柱として十分な収入で家族を支えてくれている旦那さんに弱音を吐くこともなく、孤独に任務を遂行してこられたのでしょう。しかし、問題なく平穏な日々が送れているのは、このBさんが日頃から細心の注意を払い子供達の安全を守り抜いてきた立派な成果です。これが母親業ではなく仕事であれば、十分な実績とキャリアとして給与や待遇に反映され、自他共に承認が得られるレベルの話です。子供の命を1人で守らなければいけないという状況は、24時間臨戦態勢ということです。それを約10年も当たり前のこととしてやり続けてきて、誰からも認められず終わりも見えないとなると、誰だって自分を見失いそうになるのではないでしょうか。Bさんの感じたなんとなくのモヤモヤが、私には崩壊寸前のアラートに思えたのです。誰よりもBさん自身が危機感を持たなければ、きっとこのまま無理をし続けるでしょう。そうなった場合、Bさんや子供達など大切なご家族が危険な状況に陥るという最悪の未来がいくらでも予測できてしまいます。それに気付いていただくための共感が、「完全に赤信号」=直ちに止まれ、だったのです。
Bさんはとても驚いておられました。そして自分がわがままでも変でもないことを認めてもらえて、救われたような気持ちになったそうです。何も起きていない段階でわざわざカウンセリングに来た意味とは、ご家族を心から愛するBさんだからこそ、感度の高いセンサーで敏感に危機を察知していたからだったのでしょうね。このカウンセリングが、母として妻として、自分で自分を認めてあげる機会にもなりました。
そしてそこまで理解できたBさんに、アドバイスとして夫婦旅行をご提案しました。
信頼できる人に子供達を預けて、24時間2人だけで過ごす時間を持つのです。経済的な余裕があり、夫婦仲の良好な段階ならばまだ間に合う対策です。Bさんのモヤモヤがイライラまで進行すると、この方法は使えなくなりますので、今が最後のチャンスです。「夫婦仲が良い」とわざわざ仰るのは、実際には本音を気兼ねなく言いあえる関係ではないのでしょう。もっと旦那さんに愚痴を言って甘えるよう指示したとしても実行するのはかなりの抵抗があると思われます。Bさんもそんなことを望んでいるわけではありません。子供達を守り育てる苦楽を分かち合える唯一無二のチームメイトである旦那さんと、お互いを労い感謝し合うためには、まずは親というユニフォームを脱いで重責から解放される時間と空間が必要であると考えました。これが一夜のディナーやプレゼントでは話になりません。戦士の休息なのですから、鎧を脱いでも安全であると確約された十分な時間と空間がポイントなのです。
子供の有無に関わらず、何十年と長い歳月を共に生きる夫婦の道のりは、難所の連続です。そんなご夫婦の危機を一早く察知しリスクヘッジするBさんに、我が身を顧み頭が下がる思いでした。
※実際のケースを基にしていますが、お名前や年齢などの設定は仮のものです。